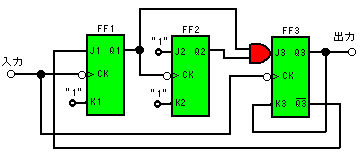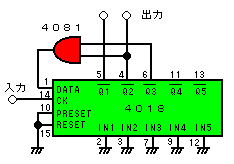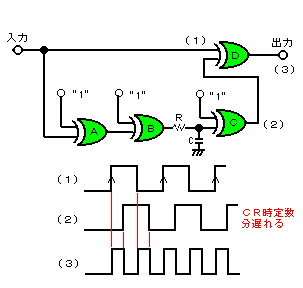たわごとのページ #30〜
 スペアナ基本講座の掲載「予告」(たわごと#30)
スペアナ基本講座の掲載「予告」(たわごと#30)
たわごと#28でも書いたように、スペアナの基本的な原理・使い方に関するホームページが、ほとんどありません。以前より東京・神田の知る人ぞ知る工学古書専門店で、たまたま見つけた古書1冊の本がありますが、たぶんもう廃刊になり入手は困難と思います。そこで、以前よりHiroさんからのご要望もあって、「お待ちかねのスペアナ基本講座」と題してスペアナの基本的な原理・使い方に関するホームページを掲載することとなりました。現在、スペアナの電子工作についての解説が進行中ですので、暇をみて随時連載していく予定です。お楽しみに。
 読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#31)
読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#31)
先日、読者の方から嬉しいメッセージと幾つかご質問を頂きました。ありがとうございます。質問の内容については、他の読者の皆様にも共通する部分があると思いましたので、「たわごとのページ」でも回答することにしました。
>大変楽しくホームページを見させて頂いています。技術的な面を、やさしく書いて頂きありがとうございます。私もある程度実用性に絶える、スペアナを作りたく思っています。
(中略)
このホームページを参考にスペアナを作りたいのですが、数点、作り始める前に質問したい内容があります。回答して頂けないでしょうか?
質問
- 最終的には、スペアナの回路とソフトは、ホームページで公開していただけますか?
- 高分解能版トラジェネの製作記事も掲載されますか?
- 最終完成時期はいつですか?
SPECTRUMホームページからの回答(一般読者向けにまとめています)
- 私の電子工作はいろいろと性能を改良していくので、最終版というのはないかもしれませんが、もちろん作った回路とソフトはホームページで公開していくつもりです。読者の皆さんが回路やソフトを自分なりにも検討・応用できるように、その回路構成に至るまでの経緯、基本的動作などの技術面もやさしくご紹介していきたいと考えています。
- 高分解能の発振回路が作れるようになれば、トラジェネにも応用できると思います。でもスペアナが完成するまでもう少し待っていて下さい。検討してみます。
- これは、難しい質問ですね。できるだけ早期に完成させたく思っています(^^;) ご紹介するからには、ある程度実用性に絶えるモノでなくては納得できません。試行錯誤の日々が続きます。さて、高分解能スペアナの性能を左右するハード面(回路)については、SPECTRUMオリジナルの反転レベルシフトPLL回路を採用することで、これまで難解であった高周波ユニット部の周波数安定性が向上できました。ここがクリアできたことによって、ハード面では概ね目処が立ってきたと考えています。あとはソフトです。PIC(マイコン)側とPC(パソコン)側のソフトを書く時間次第です。ハード面はGigaStスペアナと異なりますが、データの取り込み方法などはGigaSt準拠なので、ソフトの得意な読者からすると完成時期は早いと思います。ソフトとの兼ね合いで回路変更が生じるかと思いますが、暫定的な回路でよろしければご紹介したいと思っています。
 読者の方からの「たわごと」募集中(たわごと#32)
読者の方からの「たわごと」募集中(たわごと#32)
電子工作のホームページといっても、スペアナだけの関連情報を搭載した専門Webページ。どのように興味を持って見ていただいているのか、読者の間でも「声」を知りたいのではないでしょうか。さて、この「たわごとのページ」では、作者自身の意見を述べる場として設けてきましたが、読者の皆さんも、「声」として是非参加してもらいたいと考えています。気軽に電子メールを送ってください。匿名希望、ペンネーム・・・でも何でも構いません。特にお断りがなければ是非お名前をご紹介させてください。読者からの「たわごと」という趣旨ですので、読んでもらいたいメールの内容もスペアナに限ったことでなくてもいいです。
(注)勝手ながら公序良俗を侵害する内容は、ご希望通りに掲載できるとは限りません。ご了承ください。

 読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#33)
読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#33)
読者の方からの「たわごと紹介」続編です。山梨県の石坪さんからメッセージ&ご質問を頂きましたので、早速ご紹介したいと思います。
>10年前位までは、少し秋月のキットを作成しました。しかし、最近までは、何も作成していませんでした。最近作ったのは、H8のキットと充電器です。私も、秋月のスペアナキットを製作して、性能を上げたいと思います。しかし、住まいが山梨なので、パーツが簡単に手に入りません。そこで詳しく教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
質問
- 性能を上げられた回路は、スペアナキットとは、別に製作されましたか?
- 掃引信号発生回路もあらたに製作されましたか?
- もし、製作されていたら回路を紹介していただきいのですがいかがでしょうか?
- 趣味の機器紹介のスペアナは、秋月のスペアナキットの性能アップ版ですか?
SPECTRUMホームページからの回答
- 秋月スペアナキットを始めに購入し製作いたしました。しかし、それは実用性にはほど遠いものだったので、キットをバラして、使える部品(VCO、DBM)以外は別途購入して、別に製作しました。
- 秋月スペアナキットが実用性にほど遠い原因の一つとして、掃引信号発生回路が不安定な構成になっていると思います。従って、もう少し安定性を考慮した掃引信号発生回路を新たに設計して製作しました。
- 今後ホームページを UP DATE するときにでもご紹介します。
- 機器紹介で掲載したスペアナは、秋月スペアナキットの性能アップ版です。
 読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#34)
読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#34)
読者の方からの「たわごと紹介」続編です。石坪さんからメールを頂きましたので紹介いたします。
>回答していただき有り難う御座います。わたしの名前は、掲載していただいて問題ありません。それより、”たわごとのページ”に質問内容が掲載されていたので驚きました。秋月スペアナキットを製作するのはやめました。島田式狭帯域版スペアナ(試作品)を最初に製作したいと思います。回路等がホームページに掲載されるのを待ちます。
質問
- なぜ、UPコンバータが必要ですか?
- UPコンバータの入力は、DBMに直接負荷がつながる構造でOKですか?
SPECTRUMホームページからの回答
- スペアナの測定周波数範囲は、基本的にLO(局部発振器)の発振周波数によって決まります。従って、高い周波数までをカバーするためには、測定周波数よりも高いLO周波数(UPコンバータ)が必要になります。もしLO周波数が低いと、LO自体の高調波が測定周波数領域に飛び込んでくるため、スプリアスが増加してしまいます。
- 通常は、スプリアスを抑えるためDBMの入力にはローパスフィルタを付けます。また過大な入力に対しては、アッテネータ(減衰器)を付けます。高次の高調波を多く含まない通常の信号であれば、ローパスフィルタは付けなくても、さほど気になるスプリアスは増えませんが、アッテネータの方は付けた方がよいでしょう。DBMの原理上、−20dBm以下の小信号であれば、直接接続して測定可能です。(SPECTRUMホームページ¥狭帯域版スペアナ設計¥設計(序)¥DBMノウハウの章を参照)
 スペアナ製作のお仲間ご紹介(たわごと#35)
スペアナ製作のお仲間ご紹介(たわごと#35)
今回は、スペアナの製作に取り組んでおられる、お仲間として神戸市の岸本さんをご紹介させていただきます。先日、青山さんのホームページで、岸本さんが4GHzのスペアナに取り組んでおられることを知り、こちらからメール致しました。岸本さんのスペアナは、GigaStスペアナの観測周波数帯域の拡大を目指しています。私が目指している狭帯域化とは全く逆の立場であるところが面白いですね。
以下、SPECTRUMホームページからの質問です。
岸本さん ご無沙汰しております。
SPECTRUMホームページの島田です。GigaStの青山さんのホームページで、岸本さんが4GHzのスペアナに取り組んでおられることを知りメール致しました。ホームページ上では、その原理的なことがはっきり分からないので、一つお尋ねいたします。1G、2GもしくはUV各ユニットは確か第2世代でも変わっていないと思うのですが、ソフト的に対応できて測定周波数を拡大?ということは、どのような原理なのでしょうか。ひょっとしたら、1Gもしくは2Gの基本波での発振周波数ではなく高調波をうまく利用しているのでは?と推測はしているのですが・・もし、差し支えなければ当ホームページでも話題として取り上げたく。ご回答を宜しくお願いいたします。
以下、岸本さんからのご回答です。
島田さん御無沙汰しています!(昨年の10月以来ですね)、岸本です。
島田さんのホームページ楽しく見せて頂き、又ずいぶん参考にさせて頂いています。
>GigaStの青山さんのホームページで、岸本さんが4GHzのスペアナに取り組んでおられることを知りメール致しました。
この件については、いろいろな経緯があるのですが、全部説明すると朝までかかっても終わらないので経緯は簡単に説明します。最初Gigastがトラジェネもなかったころ青山さんはもう少しゆっくりとトラジェネの開発にかかる予定だったのですが、私が結局今回の4Gと同じようにせっついた格好になってしまい、青山さんも予定よりかなり早くトラジェネを発表する結果となりました。さてトラジェネが完成すると次に私が考えたのは以前から無線をやっていた関係で気になるのは、やはりアマチュア無線の各バンドでした。その中で〜1200MHzまでのトラジェネはすばらしいのですが、もう少し上まで伸びると1200MHz帯のバンドに届きます。
そこで今度は私が何とかしようと大それたことを考え、最初ハードの改造及び追加で対応するべく400MHz帯の発信器を製作しました。(PLL発信器で現在も島田さんのHPを参考にさせてもらっています。但し私が製作した物はBCDで直接周波数を設定するタイプです。本当はCPUを搭載してロータリエンコーダで制御出来ればかっこいい^。^
ですが私の技量と根性がついて行きません。)その後かなりたってからハードの追加改造無しで実現出来そうな考えが浮びました。これが今回の4Gの考えにも反映されています。
前置きがずいぶん長くなってしまい申しわけありません。さて本題ですが次の考えを基本に据えてします。
- 各ユニットはスペアナ用、トラジェネ用と分かれていますが、実はUVを除く全てのユニットは
・周波数変換器(アップ&ダウン)
・広帯域発信器
として動作することに着目。
- 第一世代のMIDバンドトラジェネが以下の構成で動作。
TG2G TG1G SP1G
(1406.4MHz) →(1816MHz) → (1409.6〜2009.6MHz)→1000〜1600
固定 固定 409.6MHz 掃引
以上のことからうまく各ユニットに固定発振、掃引発振の設定を行なうことにより(これは紙に周波数構成を書きながら考察しないと訳が判らなくなってきます^。^)島田さんも書かれているように第二世代でも各高周波ユニットは第一世代と全くかわりませんから、同じことが実現できます。(このMIDバンドトラジェネでは上記のように3ユニットを利用して目的の1000〜1600MHz程度の掃引を実現しています。409.6やら妙な周波数構成になっているのは出来るだけ既存のプログラムを変更しないですまそうという私の横着に起因しています^。^)これを第二世代に青山さんが取り入れてVBで実現されています。
以下に3Gと4Gの説明を加えます。
- 2000〜3000MHzの観測
利用ユニットは、TG1G、SP1G、SP2G、UVの4ユニット
第二世代で追加されたRF−SG機能を利用し、TG1Gをダウンコンバータ(2000MHz)として利用する。
・SGの周波数を593.6MHzに設定。
・2GTG本来固定の1406.4MHzの発振が想定されているので593.6の設定で1GTG単独の動作では内部で2000MHzが発生
・このTG1Gに2000〜3000MHzを入力すると−2000MHzで0〜2000MHzが出力される。これはそのままSP1Gの通常の動作である3〜1000MHzの観測で処理出来ます。
- 3000〜4000MHzの観測
利用ユニットは通常の1G、2G、UVのみでこれは簡単な原理です。
・通常の1G動作では3〜1000(1200MHz)が観測出来ますが、これは一旦1400MHzにアップコンバートされています。つまり
3〜1200 - 1400〜2600 ≒ 1400MHzです。ということ
は上式は以下のようにも考えられます。
2800〜4000 - 1400〜2600 ≒ 1400MHzとなり、逆のヘテロダインを利用しています。(実際には周波数の表示をプログラムで青山さんが変更されているようです。)
概ね以上のような顛末です。判り難い説明ですみません。(私自身がこの説明を書きながらかなり混乱してしまっています^。^)現在は更に 1.+ 2.で5000〜6200MHzが観測出来ないか考え、青山さんにメールしたところ「どこまで行くんだ!」と返事が返って来ています^。^)
ホームページも製作する予定で途中まで出来ているのですが、未だ開設にいたっていません。(出来るだけ早く開設してこの辺の説明もする予定にしています。)
p.s. 島田さんが狭帯域化を目指しておられたことが、私を観測範囲の拡大を目指させたとも言えるかもしれません。ところで全然関係のないことをお伺いしますが、(中略)
実は10GHzで動作するプリスケーラを持っているのですが分周比が1/8なのです。このまま周波数カウンタ等の前段に入れると周波数が直読できません。カウンタのベースのクロックを変える手もあると思いますが、ここは何とか1/10、1/100、1/1000等に出来ないかと考えています。そのためには4/5、2/25、1/125で動作する分周器を作れば良いのでしょうがハードで実現する方法が私の頭では判りません。もしおわかりなら唐突で申し訳無いのですが、ご教授願えませんでしょうか?。
....全然簡単な説明じゃなかったですね。ごめんなさい。....
以上、岸本さんからのメールをご紹介いたしました。
さて、GigaStのユニットに使われている周波数変換用のICですが、私が記憶しているところによるとミキサ部の仕様では、確か2.7GHzまでが周波数の上限だったように思います。4GHzまで対応できたとは驚きです。某CPUのクロックアップが流行っているように、仕様以上の使い方でも実力的には十分な余裕があることが知られています。このICの実力も4GHzまではあっても不思議ではなさそうです。5000〜6200MHzともなると、変換効率が結構低下することが予想されます。しかし、どこまでUPできるのか非常に興味があります。ホームページ開設も予定されているようで、今から待ち遠しく思います。
さて、プリスケーラに関するご質問の件です。
まず、1/1000では、1/125で動作する分周器になりますが、これは(1/5)*(1/5)*(1/5)、すなわち5進カウンタを3つシリーズに並べればと思います。5進カウンタは、図1のように3つのフリップフロップとAND回路で構成されますが、外部結線によってN(N=2〜10)分周カウンタを構成できる4018(図2)の例を示します。5分周回路を3段シリーズ構成にします。1/8分周器の出力を5分周器の入力に、その出力(どちらか一方)を2段目、そして3段目に通せば1/1000になるでしょう。ただし、10GHzという高い周波数では、1/8分周器を通しても1.25GHzにもなっています。はたして高速動作するデバイスが手に入るかどうかです。
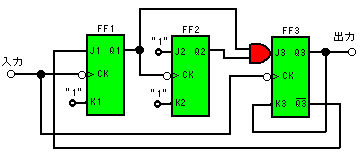 |
| 図1. 5進カウンタ |
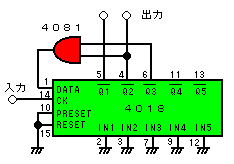 |
図2.プリセッタブルN分周カウンタ4018を用いた
5分周回路 |
次に1/10,1/100では、それぞれ4/5、2/25分周器ということですが、単なる分周器だけでの構成では少し無理かと思います。原理上、分周器は1/N(N=2,3,4・・・)というようになるからです。1/100では、5分周回路を2段にして(1/5)*(1/5)=1/25分周した後で、その出力を2逓倍する逓倍器が生じます。1/10では、5分周回路に4逓倍器が必要になってくると思います。逓倍できないとすれば分周回路の出力波形のひずみから、2次、4次高調波をフィルタ等を使って取り出し、周波数カウンタが動作する感度まで信号を増幅することになります。しかしフィルタで使用帯域が制限されるのと、まして分周器の波形は矩形波ですので、理論上2次、4次といった偶数高調波を含まないため実用的とはいえません。そこで、図3にディジタル回路を用いた逓倍器の一例を示します。動作原理は(1),(2),(3)の各波形を見てもらえば分かると思いますが、(1)と(2)の波形をCR時定数分ずらして、そのずれている期間で(3)のレベルを変化させます。したがって、入力の電圧が変化するたびに、出力が変化しますので2逓倍器になります。4逓倍器は2逓倍器を2つシリーズに並べれば理論上は可能ですが、これらの回路についても高速動作するデバイスが手に入るかどうかです。
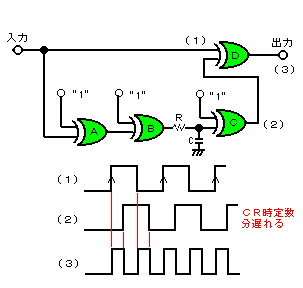 |
| 図3. ディジタル逓倍回路 |
 読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#36)
読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#36)
Hiroさんから下記のメッセージとご質問を頂きました。以前に「たわごと#28」でスペアナの動作原理や使い方を勉強したいとのことで、ホームページにスペアナの基礎講座を開設しました。
 (2001.3)基礎講座につきましては、現在リニューアル中です。Flash機能などによる豊富な動画を使って解説していきたいと考えています。
(2001.3)基礎講座につきましては、現在リニューアル中です。Flash機能などによる豊富な動画を使って解説していきたいと考えています。
以下、Hiroさんからのメールの内容をご紹介します。
>こんにちは。ホームページを拝見しました。
私が待ち望んでいました、スペアナの解説を載せて頂き、本当に助かりました。以後も、よくホームページを訪れて、スペアナの知識を増やしたいと思います。更新を楽しみにしています。
ところで、Resolution Band Width や Video
Band Widthの意味と、これらを変えたときの測定上の注意などもできればホームページか何かで教えていただけないでしょうか。
SPECTRUMホームページからの回答
ホームページをいつも見ていただきありがとうございます。スペアナの基礎講座は、連載となっていますので、ご質問の内容を網羅し、今後順次解説していきたいと思っております。さて、ご質問の件ですが簡単に回答しておきます。(詳細は、今後のスペアナの基礎講座で・・・お楽しみに!)
Resolution Band Widthは、分解能帯域幅といって、スペアナIF最終段の3dB帯域幅の意味で使われています。分解能帯域幅を狭く設定することで、ある周波数成分と近接している周波数成分の信号とが区別されて表示はできますが、一方、狭帯域フィルタは次定数が長く、したがって掃引に時間がかかるという実用上での限界が分解能帯域幅にはあります。スキャン幅および観測しやすい適当な掃引時間に見合った分解能帯域幅を選んで測定してみてください。
Video Band Widthは、ビデオフィルタの帯域幅といって、検波器の後に位置するスペアナ内部の雑音を平均化する装置に使われている低域通過フィルタの帯域幅の意味です。この帯域幅を狭くすることでスペアナ内部の雑音が平均化され、画面上で見えるノイズが低減できます。ビデオフィルタの帯域幅はスペアナの分解能帯域幅より十分狭く設定します。経験的には分解能帯域幅の約1/100程度に設定すれば効果的な平均化が得られます。ただし、AM,FM、およびパルスRF等の測定では、その復調された波形が歪んで見えてしまうことがあり、ひずまないでビデオ・フィルタを通過できるように、ビデオ・フィルタの帯域幅はIF帯域幅より広くとってやらねばなりません。このようにビデオ・フィルタは測定信号により、広い帯域幅が必要であったり、狭い帯域幅が必要であったりしますから、数種の帯域幅を切り換えるようにしてみてください。
 読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#37)
読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#37)
石坪さんからメールを頂きましたので紹介いたします。
>毎日、ホームページが変更されるのを楽しみにしています。
スペアナのパーツリスト作り始めたら問題が発生しました。アドバイスを頂けないでしょうか。
- 富士通製のMB1501が秋月では、もう、販売されていません。また、甲府の本屋に行きましたが、高周波デバイス規格表がありませんでした。すいませんが、富士通製のMB1501の代替えになるデバイスを教えて下さい。
- 入力には、ハイパスフィルターを入れた方が良いとメイルを頂きましたが、秋月のスペアナに使われているPLP-550はいかがですか?
SPECTRUMホームページからの回答
- 富士通の半導体について下記のホームページがございます。
富士通半導体データシート
http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/Device/DATASHEET/index_j.html
そこで、ページ左側の項目で、
通信用IC、
プリスケーラ内蔵PLL周波数シンセサイザ
を次々にクリックしていくと、MB15***シリーズとして、多数のICがPDFファイル形式で見られます。MB1501の代替えとして、MB1511が使えそうです。(1.1GHz対応)
- 回答したメールは、確かローパスフィルタと書いたのですが、ご確認をお願いします。
PLP-550が、550MHzのローパスフィルタであれば問題ありません。
もし入力にハイパスフィルタを入れると、それ以下の周波数は読めません。
 読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#38)
読者の方からのメッセージ&ご質問の紹介(たわごと#38)
石坪さんから返信メールを頂きましたので紹介いたします。
>こんなに早くSPECTRUM Ver1.0の回路を紹介して頂きありがとう御座います。ローパスフィルタとハイパスフィルタを間違えてご迷惑をかけました。回路構成を理解していないことがよく分かります。
スペアナ回路図紹介をみて分からない所があるので教えて下さい。
- OP1〜9は、汎用品の741程度でOKですか。
- オペアンプの電源が多岐にわたっている理由はなにかありますか。
(1)低周波増幅,検波回路のLM6361 +5V,-5V
(2)op9
+12V,-5V
(3)OP1〜8 +24V,-5V
- 回路図,挿し絵が大変上手に書いてあるのですが、何のツールを使用されていますか。
SPECTRUMホームページからの回答
- OP1〜9と記載されたOPアンプは、汎用品で構いません。
- ご指摘ありがとうございます。特に分ける必要性はありません。オペアンプ部の電源は、+24V、−5Vの2電源で構いません。こちらで試作した回路が+24V電源の電流容量が足りなかったため、+12V、+5V電源を併用しており、実際の試作回路の構成をそのまま記載しておりました。図面に注釈が必要ですね。フィルタ挿入の件も図面に反映させ、改めてSPECTRUM Ver1.1として記載しておきます。
- ホームページビルダー2001のウェブアートデザイナーを使って書いています。動きのある挿し絵はウェブアニメーターで編集しています。
 ターゲット・ボードの製作(たわごと#39)
ターゲット・ボードの製作(たわごと#39)
PIC16F877のライタ・ボードを兼ねたターゲット・ボードの製作をすることにしました。PIC16F877の入出力ピンは、ポートA〜Eまでの計33ピンあり、すべてのピンの機能を把握するには、ターゲットボードにした方が便利です。実動作テスト時に、動作を確認しやすくするために、ちょっとした工夫をしておきます。それは全入出力ピンに発光ダイオードをバッファを介して接続しておくことです。これでデバッグの時に、発光ダイオードを点灯/消灯する命令をプログラム中に追加して、プログラムの流れが目で分かるようにするとデバッグが少しやりやすくなります。なお発光ダイオードは、動作時に数mAの電流が流れるので、バッファを介して電流を供給します。直接PICに発光ダイオードを付けてしまうと、実機との接続に影響が出てしまいます。
バッファ回路ですが、発光ダイオードを駆動できるICであれば何でもOKなのですが、私のところではアナログ用のICでμPC451という単電源OPアンプがたくさんあり、ジャンクボックスの部品の整理を兼ねて、手持ちの部品を何とか利用できないものかと思いました。読者の皆さんの中には、バッファ回路になぜディジタルICを使わないんだと思う方もいると思います。しかし、このようなアナログのバッファ回路を使えば、A/D変換動作時(アナログ入力モード時)に、PICへ入力される電圧の大小により発光ダイオードの明るさが変化するので、入力電圧レベルが簡易的に分かって便利です。